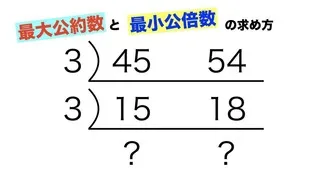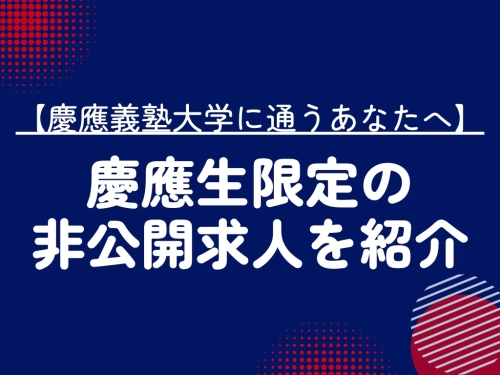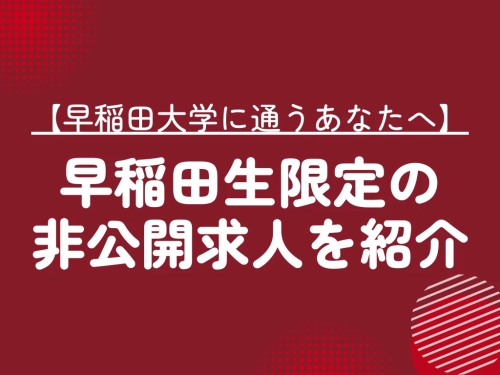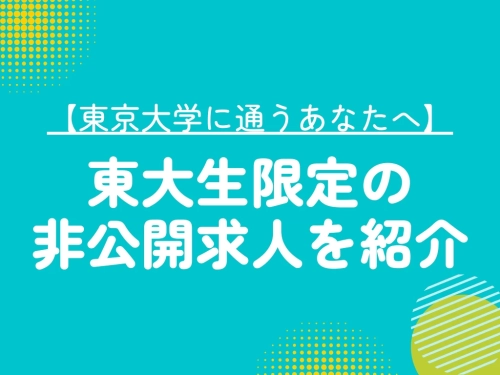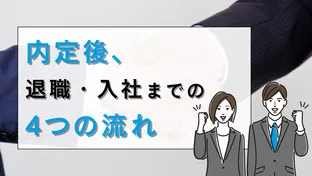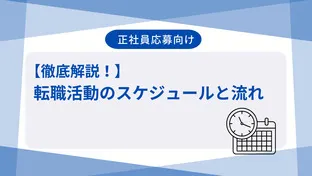「聖徳太子」が遣隋使を通して伝えたかったこと~7世紀日本と国際情勢~
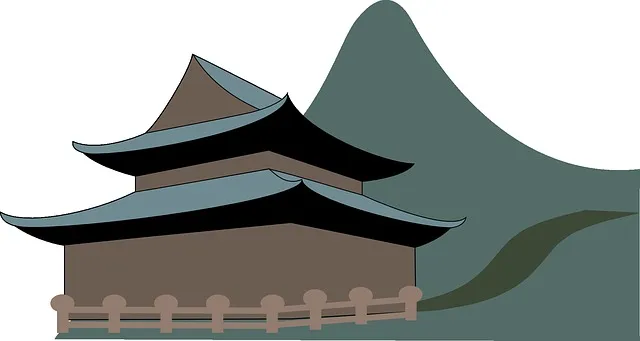
ヤマト政権
前稿「【日本史講師対象】卑弥呼の時代を教える3つのポイント! 」では、
弥生時代後半、「倭国大乱」の中で卑弥呼という女王が誕生したことや、
卑弥呼はどのような為政者だったのか、ということをご紹介しました。
本稿では卑弥呼の時代から約100年後のヤマト政権の歴史を国際関係と照らし合わせながら追うことで
ヤマト政権期の日本は古代史の中でどう位置づけられるか
を生徒にわかりやすく説明する方法をご紹介します。
コンテンツ
1.史料との向き合い方
2.5世紀から6世紀にかけての日本と国際情勢
3.遣隋使の失敗、そして・・・
4.リベンジ!第2回遣隋使
1.史料との向き合い方
前項では軽く扱いましたが、本稿でも大きく関わってくるかつ、講師の方向けの記事なので、
歴史学の基本の基本、「史料」について解説することから始めます。
卑弥呼が治めた時代、邪馬台国の存在や状況は『後漢書』東夷伝や『魏志』倭人伝という
中国の史料が根拠となっていました。
日本古代史(旧石器~弥生期)の史料は、日本国内で記したものがないからです。
しかし、『後漢書』東夷伝や『魏志』倭人伝に一貫してその存在を認める記述があるゆえ、
「卑弥呼は存在した」というのが共通の歴史認識になっているのです。
では根拠となる史料がさらに少ない場合、いかにして歴史認識をつくり上げるのか。
例えば日本国内に残っているある史料に「Aという人物がいた」と記されているとしましょう。
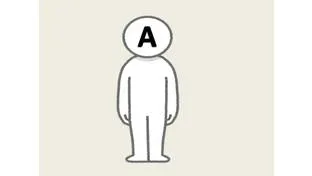
史料に書かれていても、1つの史料だけを根拠に「日本にはAがいた」とすぐ断定することはできません。
それを書く、あるいは編集した人々の何かしらの思惑によって作り上げられた人物の可能性もあるからです。
(後ほど紹介しますが、「聖徳太子」の存在にもこのような意見があります。)
そこで必要になる視点が「客観性」です。
この「A」という人物が中国の歴史書にも存在している記述があればその信ぴょう性は飛躍的に上昇します。
さらに欲を言えば、それが日本国内の他の地域の史料にも載っているなど、数が多ければ多いほど信ぴょう性
は高くなります。
歴史学者・研究者は常に、史料に「客観性」があるか疑いながら歴史認識を作り上げ、
かつ教科書なども執筆しているのです。
簡単ではありますが、以上が講師が歴史の「史料」を読むために気をつけなければならないポイントです。
本稿の内容を通して最後にまたこの点について言及するので頭の片隅に入れて読み進めて頂けたらと思います。
<ここがポイント>
史料は常に「客観性」があるかを疑って読まなければならない
2.5世紀から6世紀にかけての日本と国際情勢
卑弥呼が没したとされる248年から約100年間(300年代)は史料が残っていません。
そのため、この時期は謎の4世紀と呼ばれています。
この謎の4世紀を過ぎ、史料が再び現れる頃、日本は5世紀を迎えていました。
この時期、奈良県の大和地方に「ヤマト政権」という連合政権が誕生しています。
豪族たちによる政治体制は力を伸ばし、支配範囲は九州から北関東まで広げていました。

5世紀後半には、「倭の五王(讃・珍・済・興・武)」と呼ばれる5人の有力な大王が政権を握りました。
中でも5人目の武(=雄略天皇とされています)は、中国の南朝・宋に対して使いを送り、
服従の意を示すことによって、自らの政治的立場をより強化することを狙います。
こうした時期を経て6世紀、倭国の国づくりはようやく軌道に乗ってきました。
しかし、東アジアの国際情勢にまた変化が現れます。
589年、西晋以来「三国時代」など群雄割拠が続いていた中国に再び統一王朝「隋」が誕生します。
その勢力はとても強大であったため、東アジアに大きな影響を与えました。
国交は上記の武(雄略天皇)の時以来途絶えたまま。
きちんとした国交を開かないと隋にのみ込まれてしまう・・・
そんな可能性が十分にありました。
そこで、593年より推古天皇の摂政として政治を行っていた「聖徳太子」は外交に乗り出します。
<ここがポイント>
6世紀に強大な王朝「隋」が誕生し、外交関係を築く必要性に迫られた
3.遣隋使の失敗、そして・・・
「聖徳太子」は第1回遣隋使を600年に派遣します。
隋の皇帝・文帝に対し、使者を通して国交樹立を提案するも、断られてしまいます。
倭国の政治や制度があまりに遅れており、外交関係を結ぶような「国家」として認められなかったからです。
さて、「聖徳太子」の政策で大事なのは第2回遣隋使までの動きです。
「聖徳太子」は何とか第1回遣隋使の失敗を活かし、国としての秩序を作ろうと決意しました。
まさに国家改革です。
結論から述べると、改革を通して天皇を中心とした中央集権的な政治改革に乗り出しました。
強大な隋を相手にするには、日本も天皇を中心に1つにならなければ対抗できないと判断したからです。
そんな政治改革の代表的政策が、
603年に制定した①「冠位十二階の制」と604年の②「憲法十七条」です。
①冠位十二階の制
(推古天皇十一年)十二月の戊辰の朔壬申に、始めて冠位を行う。大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智、併せて十二階。並びに当色の絁を以て縫へり。頂は撮り総べて嚢の如くして、縁を着たり。唯元日には髻花を着く。
引用元:『日本書紀』
②憲法十七条
一に曰わく、和を以って貴しとなし、忤うこと無きを宗とせよ。人みな党あり、また達れるもの
少なし。・・・
二に曰わく、篤く三宝を敬え。三宝とは仏と法と僧となり、則ち四生の終帰、万国の極宗な
り。・・・
三に曰わく、詔を承けては必ず謹め。君をば則ち天とし、臣をば則ち地とす。・・・
四に曰わく、群卿百寮、礼をもって本とせよ。それ民を治むるの本は、かならず礼にあり。上礼な
きときは、下斉わず、下礼なきときはもって必ず罪あり。・・・
十七に曰わく、それ事は独り断むべからず。必ず衆とともによろしく論うべし。・・・
引用元:『日本書紀』
<ここがポイント>
①冠位十二階の制
これは氏姓制度によって決まっていた家柄による身分・職業制度の改革でした。
より有能な人材を登用し、国家機能を発展させる事が目的です。
氏姓制度では「家」に位を与えていましたが、冠位十二階の制では「個人」単位で冠位を与えたところが
画期的なものでした。
②「憲法十七条」
これは天皇の命令にしっかり従って働くようにという役人の心構えを示す内容です。
現代のイメージで国民全般に広く発布したものと捉える生徒がいますが、
あくまで役人対象なので誤認させないようご注意ください。
4.リベンジ!第2回遣隋使
さて、こうした改革を経ていよいよリベンジの時がやってきました。
1回目では取り合ってもらうことすらできませんでした。
607年の第2回遣隋使では、成功することができるのでしょうか。
この時、遣隋使には小野妹子が選ばれています。
小野妹子が中国の煬帝に届けた国書は非常に重要な史料なので授業でも必ず用いましょう。
大業三年、其の王多利思比孤、使を遣して朝貢す。(中略)其の国書に曰く、「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙無きや云々」と。帝、之を覧て悦ばず、鴻臚卿に謂ひて曰く、「蛮夷の書、無礼なる者有り、復た以て聞する勿れ。」と。明年、上、文林郎裴清を遣して倭国に使せしむ。
引用元:『隋書』倭国伝
大業3年とは、607年の事です。
訳の難しい部分はありませんが、指導をする際には以下の3点を最低限理解させるようにしましょう。
<ここがポイント>
①従来のような朝貢関係ではなく、対等な外交関係を求めている点遣隋使が行われるまで、日本は中国王朝に対してずっと「朝貢」
つまり服属の意志を示してその威を借りる形式でした。
それを改め、「天子」から「天子」へと対等な関係にあることを強調する文言があります。
②朝鮮半島に百済と隣接する新羅との関係を有利にするため
当時日本は朝鮮半島での利権をめぐり、新羅と対立していました。
(地政学とも関係するので、必ず日本史資料集を用いて確認しましょう。)
新羅との競争において、強国隋と対等な関係を築いておくことは国力を示すうえで大きな効果があるのです。
③隋がこの国書を許した理由
隋の皇帝・煬帝は「対等外交などもってのほか」という考えを持っていましたし、
倭国はこれまでと同じように服属している国、と位置づけていました。
ゆえに、小野妹子の手紙に対し、激怒したといわれています。
史料にも、その様子が書かれてますね。
しかし、同じ時期、隋も高句麗(朝鮮半島北部)と緊張関係にありました。
もし国書(つまり国交)を拒絶して倭国が高句麗と手を組むようなことがあれば・・・
隋にとってリスクが高くなる可能性は大きかったののです。
こうした背景から隋は倭国と対等な関係を築く以外に選択肢がない、という状態にありました。
これは決して偶然ではなく、倭国は隋の高句麗との緊張関係の時期を狙っていた、というわけです。
まとめ
以上ここまで7世紀の日本(倭国)の諸策をいかにその社会的背景と関連付けて教えるかについて述べてきました。指導の際のポイントをまとめると、
①5世紀から6世紀にかけての倭国の状況と国際情勢
・「武」(雄略天皇)の中国との外交:朝貢形式
・隋の誕生 など
②遣隋使の失敗と国内改革
・600年遣隋使で外交政策に失敗
・天皇を中心とした中央集権的な国づくりへの改革の必要性
・冠位十二階と憲法十七条
③第2回遣隋使
・小野妹子を派遣
・史料の読み込みと3つの背景
という流れで指導すれば1つ1つの因果関係が飛躍なく伝えられると思います。
本稿では「聖徳太子」と、常に「」をつけていたことにお気づきになったでしょうか。
最後にこの点について、最新の学説を踏まえてお伝えします。
最教科書をお読みの方はご存知かもしれませんが、「聖徳太子」の扱いはどんどん小さくなっています。
「聖徳太子」そのものの存在に、近年多くの疑問が投げかけられているからです。
その主たる原因の1つが、根拠となる『日本書紀』にあります。
『日本書紀』というのは朝廷が記録した史料です。
「聖徳太子」の冠位十二階や憲法十七条もこの中に書かれていました。
『日本書紀』に関わらず、史料はすべて執筆者・編者の意図が必ず入っています。
そしてそれは多くの場合自ら(国・支配者)にとって有利になるよう(家系・政治など)書かれます。
つまり、朝廷が記した『日本書紀』も、冒頭で述べたような「客観性」があるのか、
常に疑われながら研究されています。
研究の結果、現在では「聖徳太子」の存在や政治を裏付ける確実な史料はない、
という認識が共通のものになってきているのです。
さらに、推古天皇の時代に皇太子の制度は無いことや、摂政の制度も無いという見方が強いことが、
この「客観性」の怪しさに拍車をかけています。
こうした背景があって昨今では教科書でも「聖徳太子」が前面に出てこないように配慮されています。
歴史を教える講師の皆さんにも今後歴史学の最新の研究成果を踏まえて授業を行っていただきたいという
思いから最後に紹介致しました。長くなりましたが、以上です。
ここまでお読みくださりありがとうございました!


![10円玉をピカピカにしよう!![高校化学]](https://www.juku.st/cdn/article_images/304/large_juku_entry_images_image.webp)